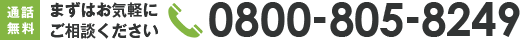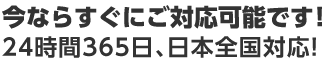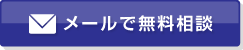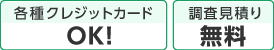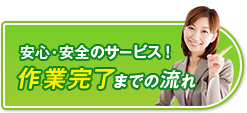枯れた芝生を手入れで復活させるには?原因と正しい手入れをご紹介!

枯れてしまった芝生を見て、どうしようもないとあきらめていませんか。枯れた芝生でも、手入れなどによってはまたきれいな状態にできることがあります。今回はその方法についてご紹介します。
芝生が枯れる原因にはいろいろあります。必ずしも手入れ不足ということではありません。そこで、芝生が枯れる原因や対処法、正しいお手入れの方法についても、この記事ではご紹介していきます。ぜひ参考にしてみてください。
目次
枯れた芝生は手入れ不足が原因?おもな原因と対処法
枯れた芝生を見ると、まず思いつく原因は手入れ不足かもしれません。しかし、枯れた芝生の原因はそれだけではありません。ここでは、芝生が枯れてしまう代表的な原因と対処法を紹介します。
手入れ不足

まずは、芝生が枯れてしまった原因が、やはり手入れ不足である場合です。水やりが足りなかったときはもちろん、肥料不足、雑草などが考えられます。芝生に雑草が多いと雑草に栄養がとられてしまい、枯れてしまうことがあります。
反対に、水や肥料の与えすぎということもあるので注意が必要です。芝生は、気温が高いときに散水すると蒸れてしまうのです。芝生は蒸れると病気にかかる可能性がありますので、気温が高い時間などに水をあげないようにしましょう。また、肥料についても濃度が高すぎると肥料焼けという症状が出ることもありますので、適切な量を与えるようにしましょう。
季節
芝生は季節によって自然に枯れるということもあります。枯れる時期は芝生の種類によってちがいます。
日本芝は冬枯れといって寒い時期に茶色く枯れます。これは夏になれば復活しますので、とくに手入れをする必要はありません。一方、西洋芝は夏に枯れます。この場合は、枯れてしまったものを復活させることはできません。きれいな芝をまた作るためには、新しい種をまいて育てなければなりません。
病気や害虫
病気や害虫が原因の場合もあります。芝生が特定の場所だけ丸く枯れているときは、病気にかかっていることが多いでしょう。この場合、まずは何の病気なのかを特定し、その病気に合った対処法をする必要があります。
害虫が原因の場合は、不規則に枯れている、芝生に鳥がよく来るにようになる、などというポイントで判断することになります。これは、芝生に害虫が発生すると卵を産み落とすからです。そうなると、羽化した幼虫が芝生を食べてしまったり、害虫がさらに新たな害虫やほかの生き物を招いてしまったりということが起こります。
芝生の踏みつけ
芝生を踏みつけたり上にものを置いたりすることも、枯れる原因になります。芝生に負荷がかかることで枯れてしまうのです。芝生はなるべく踏みつけないようにし、同じ場所にずっとものを置いておくことも避けましょう。対策として、芝生に飛び石などを敷くという方法もあります。
誤った手入れ
手入れはしているのに、誤った方法でおこなったために芝生が枯れてしまうということも、実際には起きてしまいます。以下で誤った手入れの代表的なものを紹介しますので、これまで「手入れしていたはずなのに、なぜか枯れてしまった……」という経験がある方は、思い当たることがないか確認しましょう。
芝刈り後に、時間が経っても緑の部分が伸びなくなってしまった場合は、芝刈りをした際に生長点を刈ってしまった可能性があります。生長点とは、細胞分裂を盛んにおこなう部分のことで、それを刈ってしまうと弱ってしまうのです。
とくに土壌がでこぼこしているところを芝刈り機で刈ると起こりやすくなります。くぼんだところに車輪が入ると芝刈り機の設定より低いところで刈ってしまい、生長点の下を刈り取ってしまうからです。
誤った手入れでほかに考えられるのが、除草剤の誤った使用です。除草剤には、特定の植物を枯らす「選択的除草剤」と、すべての植物を枯らす「非選択的除草剤」があります。この非選択的除草剤を使ってしまうと、除草剤をまいた後に芝生が枯れてしまいます。また、用量を守らずに多くまきすぎてしまった場合にも、芝生が刈れることがあります。
以上のように、枯れた芝生の原因にはさまざまなものがあります。季節によるものなどはよいですが、せっかく手入れをしたのに枯れてしまうということは避けたいものです。自分で手入れをするのに自信がない場合は、芝刈りや芝張りといった作業を扱っている業者に依頼して、正しくおこなってもらうとよいでしょう。
弊社では、芝刈りや除草作業、害虫駆除などもおこなっています。いつでもご相談を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
芝生を枯らさないための正しい手入れ方法
枯れた芝生の原因にはどんなものがあるか、おわかりいただけたでしょうか。それでは次に、芝生を枯らさないための正しいお手入れ方法を紹介します。
水・肥料やり

水やりの頻度は、日本芝と西洋芝でちがいます。日本芝は乾燥に強いため、夏以外は基本的には水やりは必要ありません。一方の西洋芝は、乾燥に強くないため頻繁な水やりが必要になります。しかしそれはいつも同じというわけではなく、時期によって適切な頻度があります。
たとえば春は肥料をあげた後にたっぷりと、梅雨時期は雨の合間(土壌に足跡がつくぐらいになったら)に水やりをおこないます。そして、梅雨が明けたら2日おきに、8月は高い気温による蒸れを防ぐため毎日午前中にしましょう。9月以降は乾燥が続いたら水やりをします。
時期以外にも、芝張りや補修・張り替えといった作業のあとにも水やりが必要です。まず芝張りをした後は、土が流れないぐらいの水をやります。水がしみ込んだら今度は水浸しになるぐらいにあげるのです。そのあと1月ほどは養生期間ですので、芝が乾かないぐらいの水やりでよいです。
また、種まきのあとも表面が乾かないように毎日水やりが必要です。暑い日は2回以上水やりをしてもよいでしょう。芝草が2~3㎝になるまでこれを続けます。
なお、芝生は地中の根がとても長いです。頻繁な水やりよりも、深くまで届くようにたっぷりと水やりをするほうが効果的といえるでしょう。
また、水やりと同じように悩むのが、肥料のやり方ではないでしょうか。色が濃く密に生える芝生を作るためには、やはり肥料があったほうがよいです。
肥料のやり方は、日本芝では春から夏にかけて肥料をやり、西洋芝では春と秋に月に1回肥料をやるとよいでしょう。このとき、なるべく均一にまくことがポイントです。まき方にむらがあると、芝生の色にもむらができてしまいます。
雑草取り
雑草があると栄養がとられてしまいます。そこで雑草を取る必要があります。しかし、除草剤には雑草だけを枯らす選択性のものと、雑草や作物を同時に枯らしてしまうおそれのある非選択性のものがあります。
雑草の種類によって使い分けるなど、誤った使い方をしないように気をつけましょう。芝張りの前や種まきの前には非選択制除草剤を使い、その後は個別に選択性除草剤を使用していくと効果的です。
芝刈り
長くなった芝を適切に刈ることも、元気な芝生を作るには大切です。芝生が密であることは、雑草が入ってくるのを防ぐというメリットもあります。芝刈り頻度や刈る高さも、日本芝と西洋芝でちがいますので、芝生に合った芝刈りをしましょう。また、生長点を刈ってしまわないように気をつけましょう。
サッチング
芝を刈ったり冬に枯れ落ちたりした後に、芝生の表面の部分にたまった葉や根などのことを「サッチ」といいます。サッチがたまってしまうと通気性が悪くなったり、水はけが悪くなったりしてしまうため、定期的に取り除かなければなりません。このようなサッチを取り除く作業のことを、サッチングといいます。サッチングには、レーキ(熊手)を使います。
エアレーション
芝生の上を人が歩いたりすると次第に土がつまってきています。芝生の生長具合をよくするためには、芝生に適度な穴をあけて常に新しい空気を取り込めるようにする必要があります。この穴をあけることを「エアレーション」といいます。
芝生にあける穴の間隔は、20㎝ほどにします。おこなう時期としては、芝生が弱っている夏と冬は避けたほうがいいでしょう。エアレーションには、専用の道具がホームセンターやネット通販などで販売されているため、購入することをおすすめします。
目土入れ
目土(めつち)入れとは、芝生の上に土や砂をかぶせることをいいます。目土入れには、表面のでこぼこを直す・地面の温度を保つ・新芽や茎を保護する・土壌を調整するなど、さまざまな役割があります。エアレーションのあとにも、目土を入れると効率がよくなります。
ただし、目土をかけすぎると芝の葉を覆うことになり、光合成ができなくなってしまいます。目土を入れて水やりをしたら、葉が出ているか確認しましょう。
手入れが大変なときは……
以上、芝生を枯らさないための正しいお手入れ方法を紹介してきました。思った以上に手入れが必要と感じたかもしれません。「自分では難しそう……」「暑い時期や寒い時期の作業が不安……」というように感じられたときには、業者に任せられる作業は任せてしまうと自身の負担を軽減することができます。
弊社では、芝生に関するさまざまなお困りごとにも対応しています。お気軽にご相談ください。
手入れをしても復活しない芝生は張り替えを!
芝生が枯れてしまったらまずは正しい手入れをします。しかし、それでも復活しない芝生は張り替えをしましょう。ここでは、芝生の張り替えについてみていきます。
枯れた芝生を放置するとどうなる?
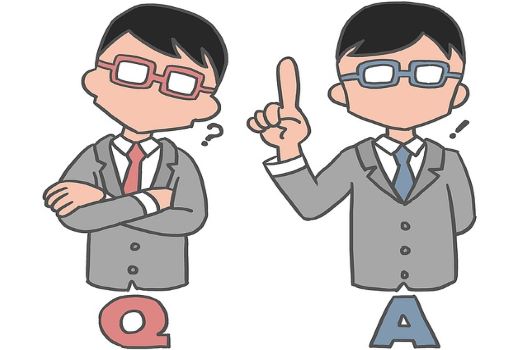
芝生が枯れたのが部分的であれば、放置しておいてもいいのではと考えるかもしれません。しかし、枯れた芝生を放置すると、周囲のまだ枯れていない芝生に悪影響を及ぼすことがあるのです。とくに枯れた原因が病害虫の場合は、被害が広がってしまいます。そこでおこなうのが、芝生の張り替えです。
張り替えに必要なもの
芝生の張り替えには、マット芝、目土、有機肥料などが必要です。いずれもホームセンターで購入することができます。また、作業をおこなうときには、スコップやシャベルなどの道具も用意しましょう。
張り替えの方法
張り替えの準備ができたら、張り替えをおこないます。手順は次のとおりです。
- 枯れた芝生の周りに切れ目を入れ、枯れた部分とその周囲を切り取ります。そして、芝生をはがしていきます。
- 枯れた原因が病害虫などでなければ、芝をはがした部分の土を耕し、肥料を入れます。原因が病害虫である場合は、土をいったん取り除き、新しい土を入れましょう。
- 土がきれいになったら、新しいマット芝を植えます。周りの高さとそろうように足で踏みしめて平らにしましょう。
- 芝生を補填できたら、周りに目土入れをしましょう。目土は芝生の葉の隙間まで入るように刷り込みます。少し盛り上がるぐらいにたっぷり目土を入れるとよいでしょう。
- 張り替えのあとは、水やりをたっぷりとしましょう。また、張り替えのあとはなるべく張り替えた芝生の上を歩かないように注意が必要です。
張り替えた芝生を維持するために
張り替えた芝生を維持するためには、定期的にきちんとしたお手入れをすることが大切です。手入れを怠ってしまうと、剥げてしまったり、でこぼこになったりするおそれがあります。最悪の場合は、枯れてしまうことも考えられるのです。
手入れをしてもどうしても芝生が枯れてしまうなど、自分で手入れをするのが難しいときには、芝生の手入れをおこなっている業者に依頼してみてはいかがでしょうか。芝生に関するプロであれば、必要な手入れを的確におこなってくれます。また、今後の手入れの仕方について相談することもできるでしょう。
弊社では、枯れた芝生についてのさまざまなご相談を受け付けています。お見積りも無料でおこなっています。24時間いつでも受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。
草刈り交換・修理の関連記事
- コナギの除草方法を解説!除草剤の使いかた・効果を高めるポイント
- 駐車場を除草するなら除草剤!使用するメリットや方法・使用時のコツ
- スベリヒユの除草には除草剤!使用時の注意・その後の雑草対策
- 草刈りは除草剤を上手に使えば楽になる!基本の使い方と注意点
- スギナ駆除は除草剤が最適!正しい散布方法と防草シートによる対策
- 庭の草刈り法が知りたい!状況別に使用する道具・再発防止の対策法
- 草刈り機ナイロンコードの巻き方|種類・特徴・選び方も確認しよう!
- 芝生の雑草の簡単な除草方法!除草剤や業者を活用してお手入れを楽に
- 下草刈りの必要性|刈りすぎて逆効果になることも!正しい時期や方法
- 芝生は手入れが大変?必要な作業とコツ・芝生以外の選択肢もご紹介!